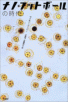2003年12月6日
「ナノ・フットボールの時代」サイモン・クーパー著 文芸春秋社 |
|
著書「サッカーの敵」で一躍有名フットボールジャーナリストとなった著者による、NumberPlusやニューズウイーク日本語版、さらには英国のオブザーバーやファイナンシャルタイムズに向けて書かれた、2002年日韓ワールドカップについての取材原稿をまとめた本である。
一つのコンセプトの元に書かれた本ではないので、全体的にテーマが散逸してしまっているのは仕方ないところだが、それでも英国ジャーナリストらしいシニカルさと、海外経験とサッカーの知識の豊富さに支えられた本質を見抜く目が見渡す情景は非常に新鮮である。例えば今大会のアイドルヒーローであるベッカムについてはこうである。
「ベッカムは典型的なエセックス族と言えるだろう・・・彼らはが好きなのは金、セックス、サッカーに速い車で本はお呼びじゃない」「英国の上流階級の間では、ベッカムを褒めるということは、自ら精神年齢が十三歳と認めることになるのだった」
どんなサッカー嫌いの日本のマスコミであっても、ここまでベッカムをけちょんけちょんにけなした人間はいないだろう。そしてその毒舌はベッカムだけに留まらない(イングランドに関しては抜きん出ているが・・・)。日本については「中盤では実に見事なのに、ロナウドの1/4の才能しかないストライカーの起用に甘んじている」、フランスやアルゼンチンの予選敗退については「チームは疲れと倦怠、慢心で敗れ去り」、イングランドのベスト4には「疲れているが倦んではいなかった」である。しかし、これがただ現実をなぞっただけの皮肉で無い事は、日本の未来を予想した最終節を見れば分かる。
「いったん海外に出たら、日本人選手は代表合流のためだからといって、むやみにアジアへ戻ってはいけない。クラブとの関係が悪くなり、スタンドが指定席ということにもなりかねないからだ」「ジーコは、徹底的な教育を必要とするやや劣った選手の指導には向かない気がする」・・・2003年末現在、状況はまさしく著者の指摘する通りになってしまっている。
では、この本は読んでいて耳に痛い箴言を聞かされて、気分が暗くなってしまう本なのかと言われればそうではない。さんざんこき下ろしたベッカムについても、ユーロ出場を決定付けるFKを決めたギリシャ戦で国民がベッカムを見直し、翌日彼の家に許しを請うために大勢の人が集まった事を書いた章で、著者はこうしめくくっている。
「ベッカムはどっちの自宅にもいない。彼はマンチェスター・ユナイテッドの練習グラウンドで、たぶんフリーキックの練習に励んでいる」
この文章が意味するものは、ベッカムの人格はサッカーとは何の関係も無く、真面目で真摯な練習だけがイングランドと98年W杯での失態から彼自身を救ったのだという事である。また、W杯中に熱狂的に日本を応援したファンについても、「ごっこをしている」「休日用のナショナリズムだ」と言いながら、終始笑顔で応援するファンに感動して宮城での敗戦で涙を流し、本国にいる友人にファンの雰囲気の素晴らしさについての感想を求めたりもしているのだ。
98年のW杯でのイングランド対アルゼンチンの試合でオーウェンが挙げたスーパーゴールについてのプレス席の様子のシーンを見てみよう。「彼らはイングランドが得点しても、普段はにこりともしない・・・ところがその夜はオーウェンが屈強なディフェンダーたちを抜き去ると、彼に賭けてでもいるように声を張り上げ机を叩いた」・・・他人を書いてはいるものの、これはまさしく彼自身の姿でもあるのだろう。
この本の、「ナノ・フットボール」という表題は、ブラジルの3Rのように、小さいスペースと時間で得点を作り出す才能が勝敗の鍵を握るという現代サッカーの真理を呼び習わした章から取っている。それは確かに夢も希望も無い絶対の真実かもしれない。しかし真理だけがサッカーではないし、サッカーの魅力は真理以外の部分にこそ豊富に存在するのである。
「試合の勝敗はナノの世界で決まる。しかし、ナノはサッカー全体と言うメガの世界から見ればほんの一部なのだ」
この「ナノ・フットボールの世界」というシニカルな題名からは、そんな著者の熱い声が聞こえてくるように思うのだ。