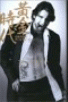2003年4月22日
「黄金時代」フローラン・ダバディ著 アシェット婦人画報社 |
|
山本五輪監督の「備忘録」と、トルシエジャパンの内部告発本としての対立軸として単純に語られる事の多いこの本だが、読んでみて思うのは「これはあくまでフローラン・ダバディについての本なんだな」という事である。
日本的な常識で言えば、代表監督の通訳という立場であれば、形式が協会に雇われているという形であっても、まず上司は監督であり、自分はなるべく表に立つことの無いように、上司の手足として必要ないことにはでしゃばらず、与えられた仕事を黙々とこなすのが普通だろう。
しかし彼は、自分は単なる通訳などではなくアドバイザーであり、「監督トルシエ」を演出、プロデュースする役目を果たしていたのだと主張する。そして、通訳としての仕事だけではないので、それを理解してもらうためにもパーソナルアシスタントという肩書きを、収入にはさほど変化が無いにもかからわず協会に認めさせたのだ。
そしてトルシエの仕事について話すときも、自分はトルシエのアシスタントだから、トルシエの味方だからと言ったステロタイプな形ではなく、人間トルシエの魅力と監督トルシエの理念と仕事に共感するという形で、そして「自分の言葉で」話している。つまり、代表監督としてスポットライトを浴び、尋常でない収入を手にしているトルシエであっても、ただの一人の人間であり対等な存在なのだという理念が第一にあるのだと思う。それは、通常のインタビュワーと監督といった形でなく、進行役兼議論相手として登場していた「トルシエTV」でも貫かれていたように見える。トルシエの方も、それがごく当然の事のように振舞っていたのを見ていて、日本的感覚で見るとそれが実に奇異に見えたものである。
その対等であろうとするスタンス、そして仕事の内容を反映させた肩書きへのこだわり、やはりこれが自己の存在、自立を重んじるフランス人の文化なのだろう。
思い返すとトルシエは就任以来、日本選手に対して自己主張や上下関係の排除、海外リーグの経験などで人間性を豊かにする事などを求めつづけていたわけだが、それらは全て傍にいたフローラン・ダバディという男がごく当たり前に体現している事でもあり、トルシエにしてみたら何故普通の事が出来ないのかという思いであっただろう。
それを我々がフランス人の傲慢さだと考える事はたやすい。しかし、日本人とフランス人の違いというものを指摘するには、両者に対する冷徹な考察無しでは不可能なのである。建前や虚構、慣習というものを当然とせずに本質を見極め、その上で良いところは認め、悪いところは己の立場関係無く主張する。それは本来、マスコミが持つべき資質ではなかったか。しかし現実は逆である。
今のジーコジャパンになって、トルシエの時のようなマスコミのバッシングは行われていないが、別の意味で思考停止になってしまっているように思えてならない。
「我思う、故に我あり」 「人間は考える葦である」
こういった偉大な哲学者達の格言を、我々も改めて噛み締めてみる必要があるのではないだろうか。