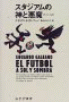2003年5月28日
「スタジアムの神と悪魔」エドゥアルド・ガレアーノ著 みすず書房 |
|
「白いヲクサマ日記」の4/24のところで絶賛されていて是非読んでみたいと思っていた本である。
原題は光と影のフットボールという名で、一言で言うならば過去の名選手や大会、いろんな事件や出来事などについて短く事実や感想をエッセイ風にまとめてある本である。とこう書くと実に無味乾燥な内容であるかのように見えるが、訳者によればウルグアイではあのノーベル賞作家であるガルシア・マルケスと双璧と目されている書き手らしく、名選手のプレイには詩と幻想が、堕落したサッカー界については諦観とアイロニーが満ち溢れた文章が並ぶ。
例えばウルグアイ選手のドリブルは作者の手にかかるとこうである。
「敵の脚のもつれを衝き、リボンを次々繰り出して犠牲者を数珠つなぎに残し、周囲の目をくらませては突破口を開く」
しかし、そういった光り輝くプレイの描写の前後には、その生みの親である選手が自分の出身であるスラムに帰りひっそりと死んでいくエピソードや、精神が病んだ肥え太りのクラブの上層部やFIFAの行状、貧しい庶民がスタンドで相手チームへの憎しみをぶつけ合うといった情景が描かれ、ほんの一筋の光を闇の部分が二重三重にも塗り固められているバームクーヘンのような様相を呈している。
この本にはW杯の各大会について書かれた章がいくつかあるのだが、始めの何行かはその年に起こった世界の出来事が述べられている。1962年大会についての章以来、その部分に必ず書かれている一文がある。
「マイアミの消息筋は、フィデル・カストロは明日にも打倒される、もはやそれは時間の問題だと報じていた」
貧困と腐敗と暴力という厳しい南米の現実。その闇が暗ければ暗いほどサッカー選手の栄光は輝き、人はその一瞬の光を生きる糧とする。しかし、それは金をむさぼる巨大な権力機構の壮大なマッチポンプであり、庶民はまやかしという檻の中でくるくる回っているコマネズミであるという自嘲がこれに象徴されている。
しかし、その自嘲さえ愛してしまっている作者のサッカーに対する情熱があるからこそ、これらの珠玉の言葉を生み出してるのも、また動かしがたい事実なのである。